 中学受験を考える親
中学受験を考える親絵本の読み聞かせを始めたけれど、実際に国語力アップにつながるの?
中学受験は、新4年生から受験勉強が本格化しますが、そのころには「国語力の差」が大きく開いています。
特に記述問題や長文読解で必要な語彙力・読解力・表現力は、短期間では伸びにくい。
だからこそ、3年生までにできるだけ差をつけておく必要があり、幼児期からの積み重ねが大事です。
その土台を自然に育てられるのが、絵本の読み聞かせ。
本記事では、幼児期からの絵本読み聞かせがもたらす学力効果と、中学受験で差がつく理由をわかりやすく解説します。
さらに、効果を最大化するための絵本の選び方、家庭で習慣化するコツも具体的に紹介。
まずは幼稚園や保育園で「言葉がよくわかる子」に育てるための第一歩を、今日から踏み出しましょう。


よしみ
塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。
夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。
幼児期の読み聞かせが中学受験の国語力に直結する理由
4年生からでは遅い?国語力の伸びる時期
中学受験の国語では、長文を読み解き、設問の意図を理解して答える力が求められますが、
この力は小4以降に急に伸びるわけではなく、知識の吸収力が高い幼児期から低学年の言語体験の量に大きく左右されます。
この時期に語彙や文脈をとらえる理解力が十分でないと、後から塾のテキストで学んでも吸収が遅くなり、難易度の高い読解問題でつまずきやすくなります。
語彙力・読解力・表現力が伸びる仕組み
絵本読み聞かせは、耳から自然に多様な語彙や文の構造を学べる機会です。
物語から登場人物の感情や行動の因果関係を理解することで、想像力と読解力が鍛えられます。
大好きな親が、「忙しい中、自分のために絵本を読んでくれる」体験から、お子さまも頑張って「聞いた言葉を自分で使おう」とするので表現力も高まります。
絵本読み聞かせがもたらす3つの学力効果
⑴語彙がぐんと増える → 知らない言葉が減る
中学受験の文章題には、日常会話では使わない語彙が頻出します。
そのため小学生になったら、中学受験用の「難しい言葉ドリル」で練習をするのですが、
幼児期から絵本で豊富な言葉に触れていると、「知らない言葉」が減り、言葉の学習や文章理解がスムーズになります。
うちの子が保育園児のときに、肉球を知っていたことを褒められました。
子供どうしの会話でも、文字で覚えた言葉を自信を持って使えるので、積極的な性格形成にも影響しました。
⑵読解力・因果関係の理解が深まる
物語は必ず「原因」と「結果」の流れがあります。
国語の読解問題は、問題文として与えられた一部の切り取り文の中から、答えを探さなくてはいけません。
中学受験の文章題では「原因」が、すぐに見つけられる文ばかりでなく、細かい表現に気づく力が必要。
読み聞かせを通じて、そのつながりを自然に学ぶことで、文章問題で問われる因果関係の把握が得意になります。
論理的な思考力も育つでしょう。
⑶表現力が豊かになり記述問題に強くなる
記述問題によっては、回答欄に文字数制限があり、自由に表現を変えて文字数を調整する力が必要になります。
絵本で覚えた言葉や表現は、自分の考えを文章にまとめる際の引き出しとなるので、
記述問題での文章の質が上がり、得点力に直結します。
また、「〇〇だから悲しくなった」などと言葉を自由に使って気持ちを表現できるようになれば、誤解を減らせてお友達との関係にもトラブルが減ります。



記述問題の部分点を取るのは得意になった
中学受験に効果的な絵本の選び方
年齢別おすすめジャンル
幼児期前半(2〜4歳):短くリズミカルな絵本
文字が少なく、繰り返しが多い本が良いです。
同じせリフが続く、ねずみくんのチョッキなどがピッタリ。
絵本の読み聞かせを始めたばかりの頃は、字も読めないし、絵にしか興味を持たない場合もあります。
絵だけをみて、ページをめくりたがるなら好きにさせてあげましょう。
幼児期後半(5〜6歳):物語性があり、感情の動きが描かれる絵本
だんだんと長い物語も楽しめるようになります。絵本から物語への移行です。
親は読むのに疲れますので、たまにでよいですが文字が多い本も読んであげましょう。
小学校低学年:やや長めで文章量の多い絵本や児童文学の入り口
市販の文字ドリル学習と並行して、数字やひらがなが読めるようになったら、お子さまが一人で読めるように促していきます。
親が忙しいときに、一人で本を開き勝手に読むようになれば理想的なゴールです。
うちの子は、かいけつゾロリのシリーズをよく読んでいました。
知識系の本もバランスよく
物語のみではなく、身の回りの知識を増やせる本も取り入れましょう。
いろいろなことに興味を持っておくと、学習の成績ついても教科別の偏りを減らせます。
漫画ですが、科学的なことを学べます。
難しい言葉もあえて取り入れる理由
簡単な言葉ばかりでは語彙の伸びが止まります。少し難しい表現や漢字も、読み聞かせを通じて耳で覚えさせましょう。



中学受験テキストに知らない言葉はほどんどなかったよ!
昔の言葉や道具に親しめます。
世界中のしかけ絵本はサブスクが便利
図書館にはなかなかない、世界のしかけ絵本も手に入れたいなら、定期配送してくれるワールドライブラリーがあります。
お子さまの成長に合わせて毎月新しい絵本が自動的に届くので、選ぶ手間が省けますし、絵本が届くたびに、ちょっとワクワクできますね。
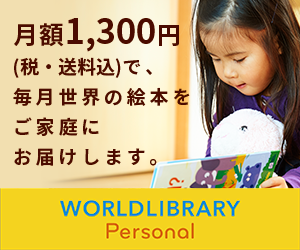
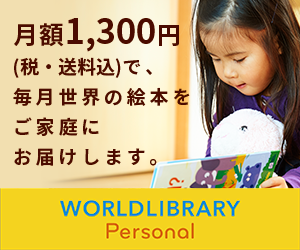
電子ブックより紙の本がおすすめの理由
- ①視力を守れる
-
テレビを近くで見ると目が悪くなると昔から言われていますので、もっと近くで見続けるタブレットなど、さらに良くありません。
うちの子は中学生以降にスマホの使用を始めましたが、幼児期はテレビから離れるように見せていただので、大学生の今でも1.5の視力をキープ。
読み聞かせ用の紙の本は図書館でも借りられますので、電子ブックより紙の本と考えましょう。
- ②五感を使って紙に慣れる体験をする
-
紙の絵本は、紙の手触りやインクの匂い、ページをめくる感覚など、五感を通して楽しむことができます。
飛び出したり、めくったり、お子さまが遊びながら楽しめるしかけ絵本の良さも、電子ブックでタップするだけでは味わえません。
中学受験のテストもまだまだ紙で受験する時代が続きます。紙と親しくなっておけば損はありません。



本はともだち
- ③親子のスキンシップができる
-
読み聞かせの際に、お子様を膝に乗せたり、ページを一緒にめくったりすることで、親子の温かい触れ合いが生まれます。
親が子供のために時間を作って本を読んであげることで、お子さまは「自分は愛されているんだ」と感じられるでしょう。



とても大切にされている気分
お子さまが小さいうちは、感想を引き出すのは難しいです。
しかし、同じ絵本を見て面白い場面で笑ったり、緊張する場面で驚いたり、感情を共有すれば親子の絆を深めることができます。
- ④文字から感情や場面を読み取る集中力を養う
-
電子ブックやYouTubeでは、分かりやすく顔の表情が変わったり、効果音に心情を支配されてしまいます。
その点、絵本は少ない絵や文からお子さまの想像力を補う必要がありますよね。
また、電子ブックの操作は子供にとって刺激が強いので、気に入ってしまうと、紙の本に物足りなさを感じてしまうでしょう。
そんなことで紙の本から離れてしまうのはもったいない。
電子ブックは、外出時など特別なときのみ使用して、紙の本のわき役にしておきましょう。
- ⑤本の内容が記憶に残りやすい
-
電子ブックでも紙の絵本でも、メインストーリーの記憶には差が出ないそうです。
しかし、紙の絵本は視覚的な情報だけでなく、紙の触覚や嗅覚などの情報も同時に伝わります。



アイスがたれて、本にシミができちゃった!甘い香りがする……
親に本を読んでもらったことや、その場面も一緒に記憶できるので、親のためにもおすすめです。
- ⑥愛着が湧きやすい
-
お気に入りの絵本ができると、「これ読んで~」と持ってくるようになり、親もやりがいがわく。
絵本を大切に扱うことを教える機会も増えるし、物を大切にする心を育むことができます
- ⑦将来の思い出になる
-
幼い頃に読んだ絵本は、お子様にとって大切な思い出になります。
親にとっても、お子さまに本を読んであげた時間はかけがえのない思い出となるのです。



あのころが人生の黄金期だったなあ……
お金をかけずに多くの本を読んであげる方法
図書館の予約システムを利用する
絵本ガイドから読みたい本のリストを作ったら、図書館のWEB予約をしていきます。
図書館には何でもあるわけではないので、リストの7割くらいしか予約できませんが、それでも十分です。
自治体によって予約できる冊数と一度に借りられる冊数が異なりますが、一人の登録で10冊から20冊になります。
お子さまの分も登録ができるので、二人分を合わせると十分な冊数の貸し出しを受けられるでしょう。
紙芝居も借りられますよ。なかなか買わないと思うのでいいですよね。
図書館には、集団の読み聞かせ用に大型の絵本や紙芝居があります。
間違えて予約しても受け取りをキャンセルできますが、図書館に迷惑をかけるので本のサイズをよく確認して予約をかけましょう。
絵本ガイドを利用する
本屋さんや図書館にはたくさんの本がありますので、どれを選べばいいのか迷ってしまいます。
そこで、絵本ガイドで選ぶのがおすすめです。私は節約のために、絵本ガイドも図書館で借りていました。
絵本ガイドに掲載の絵本は、後で図書館の予約をするために、エクセルの表に入力していくと便利です。
借りた日や読んだ日の記録をつけることもできます。
ここで紹介するのは3冊のみですが、古いガイド本でも問題なく役に立つので、図書館でも探してみてください。
老舗絵本屋店主が選ぶ100冊の絵本ガイドです。
「楽しむこと」を大切にし、選び方、読み聞かせ方、年齢別のおすすめ、絵本の役割など、幼児教育に役立つ情報が満載。
評論ではなく、分かりやすい言葉で絵本の魅力を伝えます。
子供の将来の成功と幸福に不可欠な「非認知能力」を、絵本を通して育む方法を紹介しています。
忍耐力や思いやりなど、テストで測れない内面的な力を、親子で絵本を楽しみながら伸ばせる。
絵本の選び方、読み聞かせのコツ、親の心がけを解説。
0歳から7歳の子どもと親が楽しめる絵本300冊を紹介しています。
発達や興味に合わせて年齢別に厳選し、読み聞かせのコツや、子どもの心を育む選び方を解説。
「絵本と楽しむ手づくりおやつレシピ」も掲載です。
お子さまが特に気に入った本のみ購入する
絵本を置くスペースも限られるし高額なので、手元に残しておきたい名作や、お気に入りの絵本だけを購入するといいです。
私は、Amazonで中古絵本を購入していました。
どろんこハリーは、意外と文字が多く面倒だったけど、うちの子は気に入ってました。
効果を高める読み聞かせのコツと習慣化の方法
毎日10分の積み重ねが差を生む
長時間でなくても、毎日続けることが重要。寝る前の10分など、生活の中で時間を固定すると習慣化しやすくなります。
家にいる時間が長いお母さんがお子さまの教育にあたることが多いですが、家事もあるので時間が足りません。
お父さんの手が空いてるときは、絵本を渡して読んでもらいましょう。
親の感情表現で物語が生きる
抑揚や間の取り方を工夫することで、子どもは物語に没入できる。
感情移入する経験は、読解力や想像力の育成につながります。
お子さまと一緒に遊ぶのが苦手なお父さんでも、絵本の読み聞かせなら大丈夫。
親子の温かい繋がりを育む貴重な時間になるでしょう。
忙しい日でも続けられる工夫
時間を決めて読み聞かせを習慣にする
- ①ルーティーンにしてしまう
-
読み聞かせは、お子さまに読んでほしいと言われた日だけ読むとか、親に時間ができた日だけ読むとかはいけません。
予定に入れて、毎日必ず1冊読むようにします。
幼児用ドリルと同様に、チェックリストに入れてしまうと忘れません。
- ②夜は飲みに行ったりしない
-
毎日決まった時間に読み聞かせをする習慣をつけても、お母さんの都合で飲みに行く日は中止となっては、お子さまに申し訳ありません。
飲み会で帰りが遅くなり、せっかくの習慣が崩れるくらいなら飲みに行きたくない!と自然と飲み会の価値を下げられるようになると、習慣が安定するばかりか家計の節約にもつながります。
親が疲れそうな本は避ける
絵本ガイドなどからタイトルだけを見て、図書館で予約をすると、絵本とは思えないような文字ばかりの本がたまにあります。
図書館で取り寄せ、せっかく借りたのだから、全て読まねばならないと頑張るとストレスになり続きません。
借りたら持ち帰る間に内容をチェックして、年齢に合わない本や親が気に入らない本は、返却してしまいましょう。
NHK番組のテレビ絵本もおすすめ
タブレットやスマホでからの読み聞かせには反対ですが、NHK番組のテレビ絵本は別です。ちょっと手が離せないときに、録画した作品を見せちゃいましょう。
お子さまに安心して見せられる本が選ばれているし、5分ほどで短いのもよい。
特におすすめできるのは落語家が朗読してくれる「えほん寄席」
声の表現が豊かで親も一緒に楽しめるし、お子さまは伝統話芸をたしなみ教養が広がります。
楽しい話を集めた、CD付きの本も出ていますね。DVD付きもありますよ。
実際に効果を感じた我が家の体験談
偏差値アップに繋がった読み聞かせ習慣
中学受験では国語以外の教科でも、問題文の出題意図をしっかり読み、理解してから解く必要があります。
絵本を見るとき、お子さまなりになぜだろう?と考える習慣がつけば、算数の難問にもじっくり向き合える思考力が身につくでしょう。
お子さまに成果を期待しない
親が頑張って時間を作り、お子さまに読み聞かせをすると成果を求めたくなります。
しかし、小学校受験をしない幼児期はテストを受けないので成績など分かりやすいビフォーアフターの比較ができません。
読み聞かせの効果を収穫できるのは、小学校に入学してからになるでしょう。
子どもの教育に関心の高い親のみなさまは、お子さまにペーパーの勉強もさせるでしょうから、絵本の読み聞かせのみではなく両方の作用によって学力が上がると考えています。
絵本の読み聞かせをして、近い将来に得た効果
親子で絵本の思い出ばなしをできるようになる
うちの子が高校生の時に、お友達と小さいころに読んだ絵本について話したそうです。「話に出てきた本は、だいたい知ってた」と得意げでした。
お子さまは、どの本を何冊読んだとか、細かいことは忘れてしまいますが、
さりげなく読み聞かせの苦労話をすれば、感謝されるとともに、親に愛されて続けていたと再認識し仲良くなれます。
絵本に出てきた印象深いセリフを交えた会話も楽しめる日が来るんです。
様々なジャンルの本を積極的に選ぶようになった
小学校高学年になると受験勉強が忙しくなり、ハリーポッターくらいしか読まなくなり残念。
しかし高校生になってからは、夏目漱石など硬めの小説や経済、西洋美術を理解するための宗教まで幅広く興味を持つようになりました。



日経新聞電子版もひとりで買ってるよ
理系の学部に所属していますが、理系っぽいと言われない大人になることが目標だそうです。
孫の教育にも影響する
高校生になると、自分の生い立ちを振り返るようになり、ここは良かった、あれはダメだった。と親子で子育てを振り返ることがあるんです。
子供をたたいたり、追い詰めたり、ダメだった部分も多く反省ばかりです。
しかし絵本の読み聞かせについては、プラスの記憶しかないようで自分もやりたいと言うようになってくれました。



将来こどもに本をいっぱい読んであげたいな……
親としては、子どもが将来の子育てに夢や希望を持っている状態を幸せに感じます。
まとめ:今すぐ始めたい「絵本読み聞かせ習慣」
- 幼児期の読み聞かせは、中学受験の国語力に直結
- 語彙力・読解力・表現力を同時に伸ばせる
- 毎日10分で始められ、長期的に大きな差になる
幼児期からの絵本の読み聞かせは、親子で楽しい時間を共有するだけでなく、お子さまの中学受験、その後の成長に多岐にわたる 恩恵を与えてくれます。
子どもの人生を豊かにするために、絵本を読んでたくさんの感情表現や知識を吸収してもらいましょう。
成人してからも、新しい知識を得るためには様々な本を読む必要があるので、幼少期からの読書習慣は、幸福度を追い求める力のもとになります。
お子さまと密接に関われる時期は短いので、振り返って後悔がないように時間を作って頑張ってください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。









